R3.11/16に群馬県の沼田にあるテクノエフアンドシー株式会社へ、株式会社ウッドステーションの大型パネル工場の見学をさせて頂きました。
ウッドステーションの塩地社長、ありがとうございます!

ハウスメーカーの工場を見学させてもらうこと自体が初めてだったので
それも含めて、全てが目から鱗の連続でした。
工場見学と講義で教えてもらったことと、今後、我々木材の問屋や小売の流通業はどうしていったらいいのかについて考えた事を書いていこうと思います。
なお、この業界の方にとっては読んでいて不快になる事もあるかともいます。もし不快になりそうになったら即ブラウザバックをお願いします。
前みたいにメールや直電で説教されても、私の考えは変わらないですから。
テクノエフアンドシーの工場見学
テクノエフアンドシーは超有名住宅メーカーミサワホームの主力生産工場です。
1日に12棟もの建物が24時間体制で作られています。
写真などは一切載せる事が出来ないのですが、作業工程の多くが機械化されており非常に効率的に部材が生産されていました。
まさに、圧巻です。
使用している主要木材は、フィンランドの直営工場から送られてくるスプルースがメインです。
公式サイトのトップページにある写真を見ていただくだけで規模感がなんとなくお分かりいただけると思いますが、実際はあの何倍も凄いです。
驚いたのは、組み立てている家の量に対する木材の在庫量の少なさですね。凄い回転数で回しているので在庫の必要がないのです。私のいる市場の木材在庫の1/6もなさそうな感じに見えました。
しかも、それがまるっと1日3回転するってんだから・・・・動きのない市場の在庫が馬鹿馬鹿しく見えてきます。
在来工法のウッドパネル工場の見学
ウッドステーションの工場部は、写真やSNSのシェアOKということなので公開します。

流れ作業で、図面通りに大型のパネルが組まれていきます。テクノアフアンドシーが培った治具づくりの技術が活きていました。

マニュアル化によって、大工の腕の差による品質の差が出ないようになります。
防水シートも現場では無くここで全て張ります。

本来であれば、現場ではめ込むサッシ類も、この時点で取り付けられます。

最期にラック(これに凄い秘密が)に乗せられて、このまま現場に搬入されます。

現場では、運ばれてきた順に組み立てていくだけなので、わずか数時間で屋根まで組立てられます。
まだ実際に建築の現場を見た事が無いのですが、毎日どこかしらで建っているとのことだったので、近いうちに見てみたいと思いました。
ちなみに、ウッドステーションのCADシステムの説明なども色々と教えて頂きましたが、畑違いのためなんとなくしか理解ができませんでした。
(今回は東京都市大学の小見教授とその生徒さんの為の見学会に、私たちも特別に混ぜてもらった形になっていました。)
大型ウッドパネル工場の見学を見て思った事
大型ウッドパネル工場を実際に見学させていただいて思ったことです。
小規模であれば、思いのほか広いスペースは必要なかった

ミサワホームのすさまじい生産ラインを見た後に、ウッドパネルの生産現場を見せて頂いたので余計にそう感じたのかもしれませんが、大型ウッドパネルの工場は小さい規模でやるのであれば思いのほか広いスペースは必要なさそうに思いました。
ちょっとした広さの倉庫があれば、生産ラインは簡単に作れそうです。たとえば東京木材市場の倉庫サイズであればもっと大きな規模で作れますね。(来たことある人しかわからないと思います)
木材流通の流れが新しい方向に向かう予感を感じた
今、仮に私のいる流通ルートでうまくいっている流れとして
木材問屋 → 材木店(小売り)→ プレカット工場 → 工務店
というのが、少なからずまだあります。
この辺の流れも大型ウッドパネルがもっと広まってくると完全に変わってくる予感を感じました。
プレカット工場 → 大型パネル工場 → 大工・工務店
大型ウッドパネルは「大工の仕事」を奪う?
大型ウッドパネルによる施工によって、大工の仕事が奪われるのではないか?という懸念があるかもしれません。
ですが逆に、もっと労働時間が短く、安全に、なおかつ給料が上がる仕組みが出来るようになると感じました。
労働時間が短くなる。

大型ウッドパネルを使うと現場での作業が短時間の組み立てだけになるので無駄に労働時間が延びることはなくなります。
1階が完成するのに約1時間、2階が完成するのに約1時間、屋根が全部つくまで約1時間、かかっても4時間ほどで上棟します。
現場での加工がほとんどないため、労働時間が短くなります。
大型ウッドパネルは工場で作るため、労働環境がよくなる。

大工さんが大型パネルを作るときは、現場ではなく工場で作ることになるため労働環境がよくなると感じました。
直射日光が当たらないから夏でも暑くなく、冬でも寒風にさらされることもなく、平らで、なおかつ設備が整っているところで作ることができるため、腕を上げて上や横に打ち付ける作業もなくなります。
大型ウッドパネルによる家づくりは、在来工法でいえば身体的に、明らかに楽になる印象を受けました。
はたして「奪われる」今の「大工の仕事」ってなんだ?
今の東京木材市場のお客さんから直接聞いた話ですが、いまの大工さんは自分で直接仕事を受けるのをあまり良いと思っていない人もいるようなのです。
どういうことかというと、
・在庫を持つリスク
・クレームのリスク
・ローン関係の手続きが大変
・建てた後の長期保障ができる保証がない
結果、どうなるのか?
大手ハウスメーカーの下請け作業大工になることが一番リスクが無い
というところにたどり着きます。
大手のハウスメーカーで家を建てるとしても、実際に立てているのは地場の大工さんですよね。メーカーの人が現場に来て建てているわけではないのです。
「奪われる」今の「大工の仕事」は、いいところ大手ハウスメーカーの下請けの仕事でしょうか?大手から降ってくるであれば仕事はなくならないと思いますけどね。
大工の腕とプライド
ここまで書いておいて「大工をやったこともない、お前のような人間に何が分かるのか」と思われるかもしれません。
大工さんにもプライドがありますものね。確かに私は「プレカットされた材料で小屋を建てたことがある」ぐらいの経験しかありません。
それでも、わかったことがあります。
プレカットさえされていれば「木槌」と「インパクトドライバー」で、私のような素人でも大人3、4人いれば四畳半ロフト付きの小屋ぐらいであれば1日で上棟まで建てることができるという事を。
「刻む」だけが大工の腕ではないかとは思います。上棟の先も作業は沢山あります。
ですが、新築木造の97%がプレカットで刻む必要がなくなった組み立て作業員になっているようであれば、そのプライドにはどれだけの価値があるのかと感じるのです。
「足場を組む若いお兄ちゃんのほうが早く建てられるんじゃない?」なんていわれてるんですよ。
最近、うちの近くで新築の現場がありましたが、夜遅くまで作業をする機械の音が聞こえていました。めちゃくちゃうるさかったです。
大型ウッドパネルなら、人に迷惑をかけるほど大きな音を出すような残業の必要もなくなるのになぁと。
ただ、大型ウッドパネルがもっと広がっていくと「大工さんの腕前」的なものは無くなっていきそうな予感は感じます。
プレカット&外材と相性良すぎ!
大型パネルは、木材の供給力と、品質安定性が大切です。
我々の流通は、どうしても「売り切れ」という状態が発生するのですが、プレカット工場に「品切れ」は許されません。数ヵ月先の受注まで在庫をもって、加工できるようにしています。
そのプレカット工場がメインで刻んでいるのが「外材」です。
今はウッドショックもあって外材の入荷量が少なく、価格も高騰していますが、ウッドショック前は入荷量も品質も価格もすべて高水準で安定していました。
ゆえに米松やホワイトウッドの集成材などの、俗にいう「今の日本の建築でよく使われている寸法の外材」と相性が良いです。
逆に国産材はどうなのか?
ネックは安定的な供給力と品質力です。必要な時に十分な品質で必要な量が揃えられるのか?
このへんが国産材を大型パネルに活かす課題ですね。
木材の流通業にいる人間がどのように関わっていけるのか?
我々のような「材木問屋」と、顧客である「材木屋さん」がどのように関わっていけるのか?
これを見つけることができれば、今後も生き残ることができる新たな道の一つかもしれません。
構造材はどうしてもプレカットが関わってくるので一筋縄ではいかなさそうですが、どこかしら、なにかしらの形でかかわる道を見つけられると、色々な新しい発想が生まれてきそうです。
みんなの会の事務局に入らせてもらいました。
そんなウッドステーションの塩地社長が事務局長をしている会である「みんなの会」の事務局に入れていただけることになりました。
みんなの会とは
みんなの会とは、大型パネル生産パートナー会に新設されたユーザー会です。 勉強会を通じて、木造軸組工法の近代化、森林資源との親和性を目指します。 大型パネルにご興味のある建築事業者すべてを対象とした任意団体です。
私に出来ることを精一杯やらせてもらい、色々見て、知っていく中で 衰退していくこの状況を変えていく何かが見つけられたらと考えています。
この会には伐採をされる方、から始まって大工さんまで、建築にかかわる方が多く参加されています。学生さんなんかもいます。
入会も無料で、年会費もありません。
ぜひ、材木業界の方の多くに入ってもらえると、新しい刺激になるのでいいかもしれないですよ!
家って今でも売れるんですね
今でも、一戸建てって売れるんですね。工場では当たり前のように毎日10棟以上生産していました。
データで知る住宅着工件数などでは明らかに右肩下がりですが、間違いなく需要はあることがわかりました。
市場を経由する流通ルートでの需要がないというだけということを痛感!!
このあと追記しようと思いましたが、話が反れるので別記事で書く事にしました!


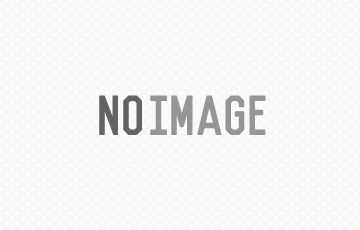



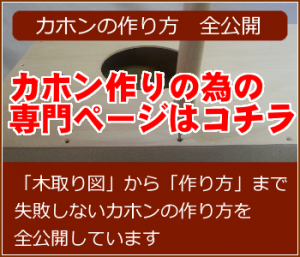
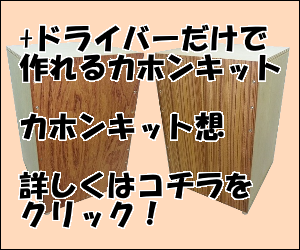

何十年もかけて国や資本力のある大手がやってきた地道な改革が今の住宅業界を作ったと思います。
施主様の事を考えるならば短い工期やコスト減や瑕疵保険、住宅性能などはなくてはならないものと考えます。
本当に勉強なしでは生き残れない時代になってきました。
しかし大工の仕事を奪い続ける事は業界全体からみればあまり良い事とは思いません。
細かな造作、リフォームでの納まりなどは大手の新築ばかりやっている職人だとできない可能性もでてきます。
とは言っても最新の工具、材木や既製品の品質などが上がってきた昨今ではそれも解消されてしまうのか・・・
木材卸・小売り業も他の業種でもそうですが一緒かもしれませんが資本主義の行き着く先は奴隷社会と言った旧ソ連のお偉いさんは先見のめいがありますね笑
コメントありがとうございます!返信が遅くなり申し訳ございませんでした!
造作に関しては、大工さんの力がまだまだ必要ですが、構造材に関して言えば完全に仕事がないですよね。
本当に、日々勉強していかないと新しい流れにどんどん取り残されていきそうです。
大工ではない何か 新しい職種が生まれる予感すらします。