和歌山県にある山長商店さんに行ってきました。

山長商店さんは、グループ会社の山長林業から紀州材の伐採
製材・プレカット加工までを一貫して行っています。
↓山長商店さんのウェブサイトはコチラ↓
とても綺麗なウェブサイトです。ぜひのぞいてみて下さい。
山長商店さんを写真付きで紹介します
せっかくご案内いただいたので写真付きで紹介します。時系列は前後するのですが、川上側から紹介します。
素材生産

まず、紀州材の生産地です。山長商店の三栖常務に案内していただきました。
写真を見てお分かりいただけるか微妙なところなのですが、紀州材はものすごい急斜面に生えています。

私が今まで見てきた生産地は、森林作業道を作りながら伐採する現場しかなかったのでこの現場を見たときは衝撃を受けました。
急斜面ゆえに、集材は架線集材になるとのことでした。
動画で撮ってきましたので見てみてください。
集材した材料は、ハーベスターで枝打ちと長さカットを行います。
こちらは360°の動画になります。急斜面感も伝わると嬉しいです。
こうして、伐採された木材は田熊の原木置き場へ
原木選別

コチラでは、丸太の上下、径、腐りなどを選別します。

山長材となる高品質な材、そうでない材はこの時点で選別されます。
人の目でしっかり見て選別していくことによって生まれる山長品質は、この時点で始まっています。
径ごとに綺麗に分けられた様子を360°みていただけます。
製材
山長商店に原木が運ばれ、製材されます。

ここにあるのは、主に105㎜角、120㎜角になる材料です。
105㎜角は主に柱、120㎜角の桧は土台になります。

皮剥き機で皮が剥かれてツインバンドソーで角材に製材されます。
製材された木材です。

太い丸太は、平角に製材されます。

どう挽くのが一番良い材料が取れるのかは、製材機を操る人の経験がものをいいます。
製材後、乾燥の窯へ
コチラは平角用。

こちらは柱、土台用です。部材によって乾燥の期間が違います。

乾燥された材料です。

少し大きめに製材されているので、さらに削って既定の寸法にします。
製材後、JASグレーディングされます。奥にいる社員さんが1本1本目視で割れや曲がりなどを確認し、山長材として出荷できるかどうかを判断したのち、グレーディングマシンに載せられます。
ここではねられた材は、プレカットにはいかず、一般の木材問屋などに行くルートに乗るとのことでした。

グレーディング
グレーディングの機械では含水率と強度を図ります。含水率はセンサーで、
コチラはヤング係数(強度)はJAS基準を満たしているけれど、含水率が高いため(20%以上)NGです。

こちらはJAS材になりますので、このまま山長プレカットのラインに乗ります。

OKの材料は自動で材に強度、含水率、産地、寸法、JASマーク、会社名、ロットNo.などが印字されます。

こちらは平角のグレーディング、よく見てもらえばわかるかと思いますがJASマークが付いているものとついていないものがあります。

素性の良い紀州材とは言え、水分が抜けきらなかったりヤングが少し足りなかったりとすべてがすべて完璧なJAS製品になるわけではありません。
JAS材を必要とする物件にはJAS材を、JASが必ずしも必要ない工務店さんにはそちらを、という形で臨機応変に対応されているようです。
山長プレカット
山長プレカットは、柱加工機、横架材加工機、羽柄加工機、ボード加工機があり、機械で対応できないものは大工さんが手で挽いています。


写真は撮り忘れましたが、プレカットされた横架材の使う場所もすべて大工さんが目で見て決めていました。
部屋に入った時に、節が目立たないようにすることや、木の曲がる応力によって使う場所を書き込んでいました。まさに経験とみる力です。
プレカットされた材料はこの矢印のある場所に保管され、順次現場に運ばれます。
(個人情報が絡んでくる関係上、写真が取れませんでした)

見学させていただいて感じた事
1つ目は「山長の見る力の凄さ」2つ目は「家はガンガン建っていること」3つ目は「自社の当たり前は外から見たらなんとかできることも多そう」という3点の気づきがありました。
山長の見る力の凄さ
川上の時点からとにかく人の目で見る力が凄いと感じました。
原木の時点で腐りや曲がりを撥ね、平角は熟練の社員が目で見て最良のものを挽き、JAS材のグレーディング前に目視で選別を行い、プレカットされたものの現場の配置も熟練の大工さんが決める。
全て、人の目で見る力で撥ねたり、挽いたり、決めたりと、人の「見る力」がとにかくすごいと感じました。
紀州材を、高品質な山長ブランドとして高単価で販売できるのもこの人の力あってこそ、システムや機械では対応しきれない。
そんな「見る力」の凄さを感じました。
家はガンガン建っている
市場にいると構造材が売れないため全く実感できないのですが、今も家はガンガン建ってます。
プレカットの日程表を見せていただきましたが、向こう2ヶ月ぐらいの加工日程がビー-ッチリ埋まってました。
「着工戸数が減っている」だの「新築は売れない」だの言われているので、市場で木材が売れないのかと思っていましたがそうでななく、家は建ってます。
仕事のある大工さん・工務店さんは忙しいんです。
山長商店さんでは丸太で3万1千~2千リューベの丸太を使っています。つまり「木がそれだけ売れている」ということです。
工場の様子を見て、改めて木材市場が木材の流通のメインルートではなくなっているのを改めてまざまざと実感させられました。
家は、まだまだガンガン建ってます。
自社の当たり前は、外から見たらなんとかできることも多そう
会議の中で話していて感じたのは、仕事のやり方を変えるだけで効率化を図ることができることも多そうだなぁということです。
今まで当たり前のようにやってきた仕事、教えられたようにやる仕事は、それが当たり前になってしまうので改善案も浮かばない事が多いです。
なぜなら、それが「当たり前だから」
例えば、棚卸作業。野帳をもって大人数で1つづつ手書きしていくより、もっと効率的でいい方法がありそうな気がします。
いざ「どうやったらもっと効率が良くなると思う?」なんて聞かれても、何の案も出てこないことが多いです。
昔働いていた本屋でも、一時期「効率改善報告書」だかなんだかを週1回提出しなければならない事があったのですが、もちろん当たり前にやっている業務の中でびっくりするぐらいの改善案は出るわけもなく、廃れていった記憶があります。
システムの力でなんとかできることも多いかと思いますが外から見ると、その前に業務の改善によって効率化を図れることも多そうだと感じました。
お礼
今回、見学させていただくにあたって、ウッドステーションの塩地会長、佐藤さん、山長商店の榎本長治社長、三栖さん、大迫さん、松田さん、野村さん、山長林業の佐武さん、SEの柳川さんには大変お世話になりました。
システム的な知識でいえば、まだ簡単なスマホのアプリを作ったり、VBやC#で簡単なコードを書くことしかできませんが、業務改善のお手伝いのお力になれるよう尽力していければと考えております。


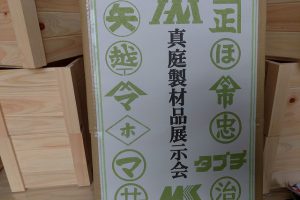
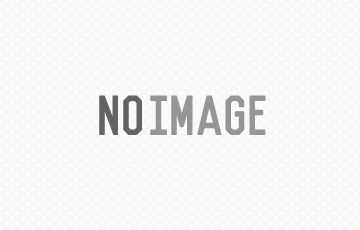

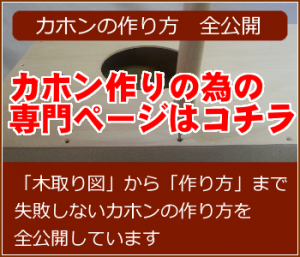
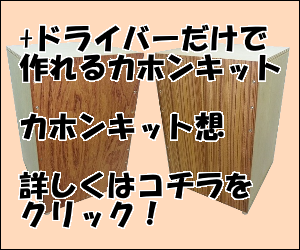

コメントを残す