10/26~10/28に開催されたJASセミナーのレポートです。

セミナーの様子を3分に まとめて動画にしました。是非ご覧くださいませ。
なお、ご参加いただいた方にはセミナー参加特典として事前に取材した見学場所の説明動画が閲覧できるようになっています。
開催場所や見学場所が違うかもしれませんが来年度もセミナーは開催されると思います。
下のページの次年度セミナー事前告知のご連絡にお名前とメールアドレスだけでも登録いただけると事前に連絡させていただけますので、ご利用いただければと思います。
私主催の物ではないのでセミナーの内容自体は書けませんが、今回のJASセミナーで私が感じた事や学んだ事を書かせていただきます。
①木材製品問屋と木材小売は商流からはじかれている。
私のいる東京木材市場をはじめ、木材製品問屋とその顧客である木材の小売業は、いまや完全にメインの商流からはじかれていることを改めて再認識しました。
いまや、新築の木造建築の約97%がプレカットですからね。
大工さんが刻まないこの時代に、未だに大工さんの刻みが必要な材料を扱っているのだから商流からはじかれて当たり前っちゃ当たり前なんですけど。
プレカットが生まれる前の商流

プレカットが生まれる前の商流は
製材所→製品問屋→材木店小売→大工・工務店→施主
と地域の腕のいい大工さんに家を建ててもらうのが一種のステータスのような状態でした。木材の品質は材木屋さんや大工さんが担保してくれていました。
プレカットが生まれてすぐの期間の商流

製材所→製品問屋→木材小売→プレカット工場→大工・工務店→施主
材木の小売り屋さんに現場に納入される前のプレカットされた材料が置いてあるところをよくみました。
材木の小売り屋さんから、材料をプレカットに入れて刻んでいたのですね。材料の良し悪しを担保していたのはこの時点では材木屋さんになっていたのではないかと思います。
今の商流

原木→製材所→プレカット→ハウスメーカー→施主
ハウスメーカーからの図面通りにプレカット工場が材料を刻みます。材料は製材所からかなりの量が直送されています。
木材の品質は、乾燥処理を含めて製材所によって担保されています。完全に流通のルートから外れちゃってますね。
プレカット工場は、私たちが扱う量の何十倍もの構造材を仕入れ、出荷していることが見学するなかでわかりました。

流通業はいらないのか?
なくなると困る人はいるのでいらなくなることは無いと思いますが、さらに仕事は細かく、狭いパイを取り合うようになるでしょうね。
すでにベニヤ数枚、垂木数束とかで配達している状態なので、それがさらに細かくなって垂木数本とかで配達とかになるのでしょうか。もしくは、もうそんな状態になってるのかな?
不動産収入などでもない限り、他の事業収益になり得そうな「新しい何か」を始めないとヤバいですね。
今のお客さんが、いつまでもいてくれるとは限りません。
②大型パネルなど木材流通の「新しい流れ」がすさまじい
2日目の座学で、ウッドステーションの塩地社長の大型パネルについての講義がありました。

新たな木材流通の流れが、確実にきています。
話も面白いし、説得力も凄い。
塩地社長の講義は、話も面白いし、説得力も凄かったです。
「大型パネルが全ての問題を解決できる」
それが当たり前の事だという確信をもって話をされる姿は、聴いている人たちを引き付けていたと感じます。
木材の価格から大工さんの収入アップまで一貫して考えられており、確かに森を救える仕組みが完全に出来上がっていると感じました。
大工、林業従事者だけでなく、世界をも救えそうに感じました。
もはや大型パネルの入り込めない狭小住宅エリアだけで戦うぐらいしか弱点が見つからないです。
そういった新しい流れが木材業界を良い方向に向かわせてくれるのだと思います。市場はもはや関係なくなっちゃうんですけどね。(すでに商流からはぶかれているから今更なんだってのはありますが)
塩地社長の大型パネルのように、あらたな木材流通の流れが革新的過ぎます。
実際に話を聞くと流通業の我々も、何か考えてやらないとヤバい状態だと感じるはずです。
③JAS製材品は、あまりにも「もんやり」しすぎてる
スタッフをしていた立場でこれを書くのはどうかとも思ったのですが、JAS製材品について思うことが多かったので2点ほど書かせていただく事にしました。
目視等級、無くせばいいのに
座学の講座の中でJASについて学ぶ単元があるのですが、JAS製材品は細かく分かれて、基準もしっかりしてそうに見えるのですが、よく考えると「もんやり」していると感じました。
特に目視等級というやつ。
JAS製材品には、大きく分けて「機械等級」と「目視等級」の2つがあります。
機械等級は、グレーディングマシンで強度と乾燥具合を測定し表示され出荷されます。目視等級は節の大きさや数を目で見て測定し表示され出荷されます。
目視等級の強度は、ざっくりいうと「節が少ないから強度も高いでしょ」という考えからきているようで、機械で測っているわけではないので本当の強度はどうなのか実は分かりません。
機械等級で1本1本測って出てきたJAS製材品の方が性能を担保されているような気がしますね。
日本には今、約4800社の製材所があるようで、その中でJAS材の出荷認定がとれているのは約600社です。さらに機械等級で出せる製材所は90社しかありません。
製材所がJASを維持するのはコスト的に合わないらしく、JASを辞めてしまう所も多いです。実際に新木場相原の取引先はJAS認定工場がなくなりました。(製材所は通常通りやってます。JASを返納しただけです)
JAS材の普及を国が本気でやりたいのであれば、補助金の使い道はここだと私は思うんですよね。
全てのJAS製材所に乾燥機&グレーディングマシン補助で設置させて機械等級をスタンダードにすればいいのに。そして、維持費も補助で補って製材所の負担を軽くすればいいのに。
なんて、スタッフ席でセミナーを聞きながら考えてました。
「目視等級」と「機械等級」のダブルスタンダードは講義をしてくれた建築士の古川さんもJASの問題の1つだと言ってましたが、たしかにそのとおりだと思います。
JAS材強制にすればいいのに
消費税増税みたいなノリで、国内の木造建築を全て強制的にJAS材強制にすればいいのに…
なんて思っちゃいました。
業界にも政治の世界にも目に見えない大きな力がたくさん複雑に絡み合っているんでしょうけど、全国民に影響がある消費税増税だって、あっさりと「えいっ!」って感じでやれるんだから
やってやれないことはなさそうに感じますけどね。
「別にJAS材でなくても良い」からJASが使われないというのも原因の一つだと思うんです。
JAS材は品質を担保しているかもしれませんが、JASがついていない製材所独自の品質担保品でも十分だからこそJASが普及しないんでしょうね。JASマークがつくと価格が上がりますし。(ここが一番大きな理由かもしれないです)
その証拠に、市場でJAS材が欲しい!と、ここ9年で一度も言われたことがないです。
本当に広めたいのであれば、強制JASの仕組みでも作ればいいのに。と講義を聞いていて思ってました。
他にも、JAS材が普及していかない理由はたくさん思いつきますが、今回はこの辺で。
④山側の方にお金を落とせないと何も解決しない。
山にお金が回らないと、再造林も出来ませんし、今の補助金ありきの事業から抜け出すことができません。
逆に言えば、今の倍の価格で安定的に原木が売れる仕組みができれば、山林所有者も儲かりますし林業をやっていこうという人も増えるはずです。
そもそも、伐採する業者は補助金対象以上に伐採量を増やすと切れば切るほど赤字になるため補助金のリミットいっぱいまでしか伐採しないようです。
これでは生産量が増える訳も無く。
それどころか、建築に使える木材もバイオマス発電などに持っていかれている始末。
まさに塩地社長のいう所の「山火事産業」です。
山にお金が回らないとその先の何も解決できません。
⑤ウッドショックに関係ある材料はしょせん外材の代わりのもの。
コロナの影響で木材不足のウッドショック状態です。しかしながらウッドショックに関係のある材は外材の代わりのものです。
例えば、外材依存度が高い 柱、梁、桁、土台などの構造材がそれにあたります。
柱は、ホワイトウッドの集成材、梁はベイマツ、土台はベイツガ等ですね。
これらの輸入が少なくなった為、これらが国産材に一時的に変わっている状態といえるでしょう。私の予想ですが、輸入木材の流通が元に戻るようなことになるれば、また当たり前のように輸入木材が使われるようになるんじゃないかと思います。すでに使い慣れてますからね。
ウッドショックに関係のある材は外材のかわりです。
二次被害を受けている物もあります。
ウッドショックの影響で原木が取り合いになっている影響もあって、製材所が満足に原木を仕入れる事が難しくなっている影響で、バタ角や貫などの羽柄材も量が少なくなり、値段が高くなっています。
まさに二次被害です。
ウッドショックに関係ない物もありますが…
ウッドショックで木が無いと言われているけれど、一枚板や、役物などは在庫あります。
需要が出ないと、必要が無いという良い例ですね。
逆に役物の値段が落ちていますが、それでも役物が売れるわけではなく「値段が同じならいつもの一等材の方が良い」という状態になっています。
普通であれば、「値段が同じで物がイイならラッキー!」となりそうなものですが、もしお客さんに「前と同じのを前と同じ値段で持って来い」と言われると、そのときにも同じものが同じ値段で手に入るとは限らないからです。
だったら、値段が同じなら一等材の方がよいとなってしまい、結局役物に需要が無くなってしまうんです。
次年度も開催する予定です!
学べること、気づきが非常に多いセミナーです。

来年度も開催する予定となっておりますので、もし「タイミングが合わずに参加できなかった」「興味はあったけど参加するのに迷った」そんな方がいらっしゃいましたら以下のリンクから開催日が決定次第事前連絡するフォームがございますので、ぜひお名前とメールアドレスだけでもご登録をいただけると嬉しいです。
木材や森林、建築に直接関係のない方の参加もありましたので、気になりましたら是非ご参加いただけると嬉しいです。
来年はコロナが終息して、夜にお酒でも飲みながら語り合えるイベントにできたら素敵だと思います。



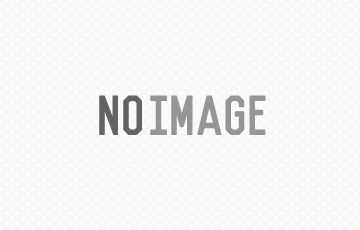
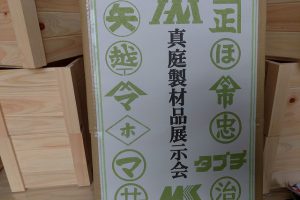



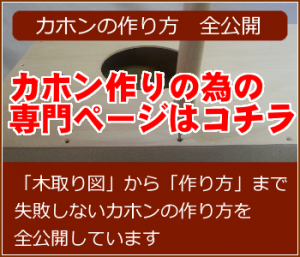
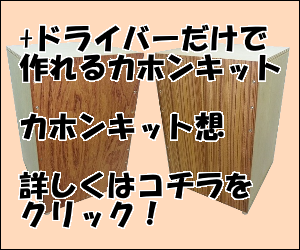

ありがとうございました。
来年も是非参加したいです。
浅野さん、コメントありがとうございます!!!!
また、来年も是非お願いいたしますm(_ _)m