材木は、地域によって使う寸法が違います。
例えば、貫(ぬき)と呼ばれる板

都内で主に使われているのは
13mm × 90mm × 3650mm
という寸法です。
これは地域によって使用する厚みが変わります。
千葉県は15㎜ 18㎜
茨城県は14㎜ 18㎜
あたりがメインでしょうかね。
材木問屋が材木屋さんに材木を売る時は
一枚いくら ではなく、リューベいくら になります。
リューベ(立米)とは材積の事です。体積みたいなものですね。
例えば
「105㎜ × 105㎜ × 3000㎜の柱がリューベ100万円だよ!」ってなると
「えぇっ!?100万もするの!?」ってなると思いますが
リューベ単価は材積計算なので、一本あたりの単価は33100円ぐらいになります。
同じ幅と長さの寸法であれば、薄くなればなるほど
1枚あたりの単価が安くなります。
東京で使われる貫(ぬき)はなぜ13㎜になったんですかね?
もしかして、コストダウンの為かな?
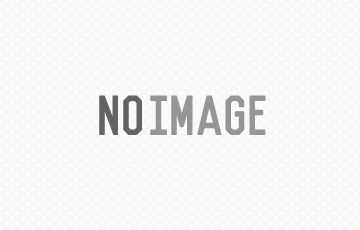
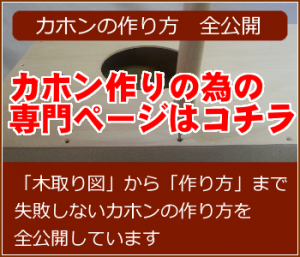
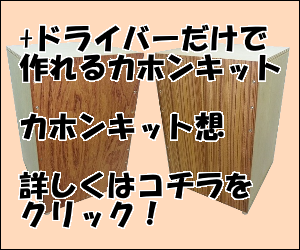

コメントを残す